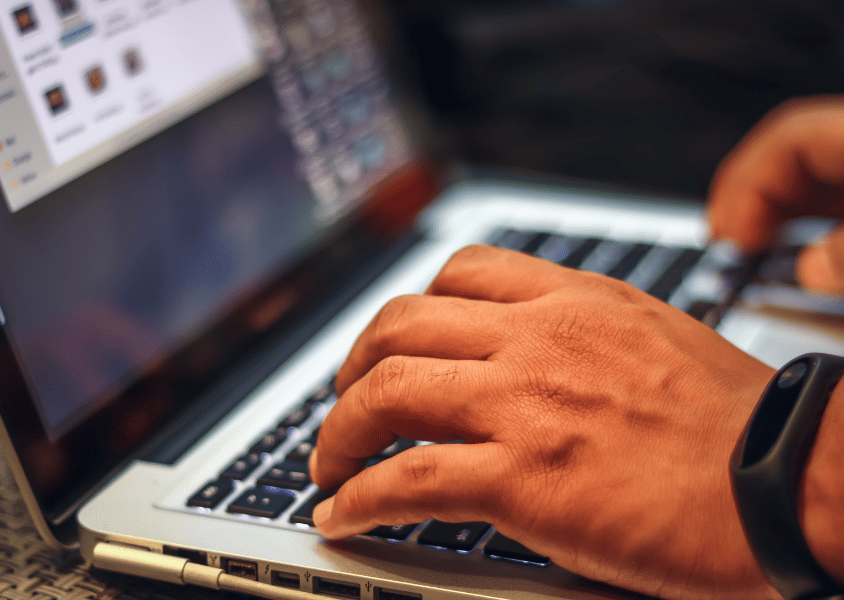「DXの導入に興味があるけど、何から手をつけたらいいのか分からない。」
「DXが自社にどういう風に使えるのかがイメージできない。」
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
DXという言葉はよくメディアでも見かけますが、あまり言葉の意味をよく理解できない方や、具体的にイメージしづらい方もいることでしょう。
そんな方向けに、この記事ではDXについて分かりやすく説明した上で、実際に企業がどのようにDXを導入しているかを示す事例やDXを進めるにあたって必要なことを紹介していきます。
この記事を読むことで、言葉の意味がわかるようになるだけでなく、DXを進めるアイディアに日頃からアンテナを貼り続けられるようになるでしょう。
おさらい!DXとは
DXとは、AIやIOTなどのデジタル技術を用いて従来のビジネスを変革することです。膨大なデータやそれを処理するデジタル技術を元に顧客のニーズを分析し、サービスやビジネスモデル、組織のあり方などを改革することを指します。
コンビニの自動決済システムやコールセンターの自動音声などがDXの一例で、ここ最近はかなり身近になったと感じる方も多いでしょう。人件費の削減や販売促進による売上の増加など、収益に直結する事例も多数あります。
変化と競争が激しい情報社会についていくべく、今、多くの企業がDX化に力を入れ始めているのです。
DXの事例
では実際、どのようにDXが取り入れられているのでしょうか?
ここでは、3つの事例を紹介するので、あなたの会社が抱えている課題と照らし合わせながら読み進めてみてくださいね。
事例①:もりやま園株式会社
100年以上続くりんご農家のもりやま園株式会社。「農業を成長産業に変える」を経営理念とし、りんごの生産性向上のためにDX化を進めています。
もりやま園株式会社は、これまで感覚的にしか捉えられなかった農作業の詳細をDXによって見える化することに成功。果樹に特化したクラウドアプリケーションを開発し、作業ごとにかかっている時間を割り出せるようになったのです。
全作業の約75%が剪定・摘果・摘葉など、廃棄するだけの作業だということが分かり、その時間をより生産的な時間へ転換しようと舵を切りました。現在は、地域生産者とのオープンイノベーションに取り組み始めています。
農業は感覚的に作業を進めることが多いので、DXによって数値化すると新たな気づきが得られやすいかもしれません。
事例②:秋田酒類製造株式会社
秋田酒類製造株式会社は、秋田流酒作りの技法を守る清酒の製造元。東北最大級の清酒の出荷量を誇ります。
DX化を試みたのは、製造現場の状況を遠隔で確認できるシステムの構築。それにより、時間外労働をせざるを得ない状況にあった杜氏や蔵人の業務の効率化・省力化を図りました。
直近の課題は、IOTに関する知識と技術をもった内部人材を育成すること。秋田酒類製造株式会社は、DXに関するシステムを年々増やしており、今後も更なるDXの拡張を予定しています。
収益を上げるには、売上を伸ばすかコストを削減するかの2択。DXによって人手では不可能であったコスト削減に成功する可能性があります。
DX導入にかかる費用よりも、削減できるコストが上回るのであれば、収益が上がる可能性があるので、ぜひDXの検討を進めてみてくださいね!
事例③:四国情報管理センター株式会社
高知県のオープンイノベーションプラットフォームに参加し、積極的に地域課題に関与している四国情報管理センター株式会社。地方都市が抱える課題を解決するために、DX事業に注力している会社です。
この会社が取り組む、以下の2つのDX事例をご紹介します。
・売れ行き状況の可視化による直販所の販売促進
・競馬場における放馬の早期探知
売れ行き状況の可視化による直販所の販売促進
直販所の商品棚にカメラを設置し、SNSを通じて売れ行き状況を配信。それにより、生産者の出品意欲を高めたり、購入者の購入意欲を高めたりする効果が得られています。
新しい商品が並んだ時、わざわざSNSで投稿を作るのも手間がかかるものです。店内の状況を配信していると、お客さんには説明なしで新しい商品が入っていることが伝わるので、販売するための労力を減らせます。
お客さんにとっても、店に行かなくてもどんな商品が販売されているのかを確認できるのは嬉しいポイントですよね!
競馬場における放馬の早期探知
AIを用いて放馬を自動的に探知し、担当者のスマートフォンに通知することで放馬を早期検出できるDXを導入しました。放馬とは、騎手を振り落として馬が逸走してしまうことです。
コントロール不能になった馬を放置するのは危険なので、DXが導入されるまでは、放馬を検出するために多くのカメラ画像を24時間監視する必要がありました。
DXにより、常にカメラを監視する必要がなくなるので、人的なコストを削減することに成功しています。
DX化、DXをするために必要なこと
ここでは、DXするにあたって必要な3つのことを紹介していきます。
デジタル技術とビジネスの理解
ITがビジネスでどう活用されているのかを理解することが重要です。ついついAIや5Gなどの最新技術に目がいってしまいがちですが、ITはあくまで手段にすぎません。重要なのは目的です。
まずは上記にも紹介したように、DX化の事例を参考にロールモデルを探すところから始めてみましょう。そこから、ITがどんな役割を果たしているのか、それによって何が解決されているのかを理解することが重要です。
なので、IT活用の事例を日々キャッチアップするのを心がけておきましょう。
デジタル人材
DXを進めるには、デジタル人材が必須です。デジタル人材とは、最先端のデジタル技術を活用して企業に対して新たな価値提供ができる人材のことをいいます。デジタル人材がいなければ、たとえIT技術があったとしてもそれを運用できません。
デジタル人材を確保するには、外部人材に業務を委託するか、内部人材を育成するかの2つの選択肢があります。内部人材の育成には人材を確保し、育成するのに多くのコストがかかるので、DXの方向性が固まるまでは外部に委託するのがオススメ。
また、デジタル技術を持っているだけでなく、プロジェクトを推進できる能力を持った人材が必要となるでしょう。DXを導入するにあたって、さまざまな壁にぶつかります。厳しい状況下においても、適切に課題を理解し、解決策を設計できる人材が必要です。
信頼できる相談者
とは言っても、あなたの会社に合ったデジタル人材を確保するのは難しいかもしれません。ですので、まずは信頼できる相談者を探してみましょう。
友人でもいいですし、税理士や銀行の担当者、地元の商工会などで相談してみると思わぬ出会いに遭遇するかもしれません。
普段のコミュニケーションの中で、DXに関する相談をしてみるのもいいかもしれませんよ。
まとめ
いかがだったでしょうか?この記事の内容をおさらいすると、以下のようになります。
・DXとは、デジタル技術を利用した従来のビジネスを変革すること
・農作業を見える化することで無駄な時間が明確になった事例
・製造現場にDXを導入し、業務の効率化・省力化を図った事例
・商品棚にカメラを設置し、販売を促進させた事例
・ロールモデルを見つけ、情報を日々キャッチアップすることが大切
・プロジェクトを進められるデジタル人材が必要
・信頼できる人に相談してみましょう
DX事業を進めている企業の事例を多様な分野から紹介してきました。いくつか事例を知るだけで、DXのイメージがついてくるのを実感していただけたかと思います。
大切なことは、あなたの会社でどうDXを活用するかということです。それはすぐには見つからないかもしれないので、日頃から情報をキャッチし続けてみましょう。
きっと、あなたの会社が参考にできる事例が見つかることでしょう。
最後までお読みくださりありがとうございます!